
アニメーションエンジニア 新川 昌典
学生時代から続く「物理シミュレーション」への探求心
―まずは現在の所属と業務内容を教えてください
現在、内製ゲームエンジン開発室に所属しており、主にアニメーション機能の開発や、内製ゲームエンジンを使用しているプロジェクトのサポートを行っております。
また、『鉄拳8』で採用されている内製のクロスシミュレーションというものも開発しています。
クロスシミュレーションというのは、キャラクターの衣服などの物理挙動を計算する技術の事です。昨年の「CEDEC2024」や「SIGGRAPH Asia 2024」では、その内製クロスシミュレーションに関して講演の機会もいただきました。
▶CEDEC2024:『鉄拳8』の揺れもの表現を支えた内製クロスシミュレーション
―新川さんは学生の頃から物理や数学分野の研究をされていたのですよね。
はい。自分は、高専・大学・大学院と物理シミュレーション系の研究を行っていました。
物理に関しては、高専に入ってから学びましたね。元々コンピューター周りの事が好きで、中学生のころに進学先を探しているうちに高専というものを知り、実際に入学したらより視野が広がって「物理系の分野に興味がある」と感じ、専門的に学んでいくようになりました。
高専から大学院まで、自分が通っていた学校はどこも結構好きなことをやらせてくれる所でした。
高専だと、GPUを使った流体…例えば水や空気といったものの物理シミュレーションを研究していました。GPUを使った物理シミュレーションというのは今でこそ普通ですが、当時はまだまだ最先端でしたね。
そして、大学では結構変なことをやっており…(笑)
カタツムリやナメクジが粘液を使いながら壁を這ったり、前に進んだりするための筋肉の動きを、物理シミュレーションで再現していました。実はカタツムリやナメクジは苦手だったのですが、だからこそ興味が湧いたというか…面白そうだと思って研究をしてみたというのがきっかけです。
大学院になるとまた研究対象は変わり、今度は「体積の変わる流体」を研究していきました。
例えば、ペットボトルの炭酸が急に膨れ上がるような現象を物理シミュレーションで作れるようにする、というような研究を行っていました。
―興味・関心を持った様々なことを突き詰めて研究されていたのですね。
そうですね。ただ、研究というのは今までやられていないこと・新しいことをやらないといけないので、何がまだ研究されていないのかを調べつつ、かつ自分の興味があるということを両立できる分野を探し、取り組んでいきました。
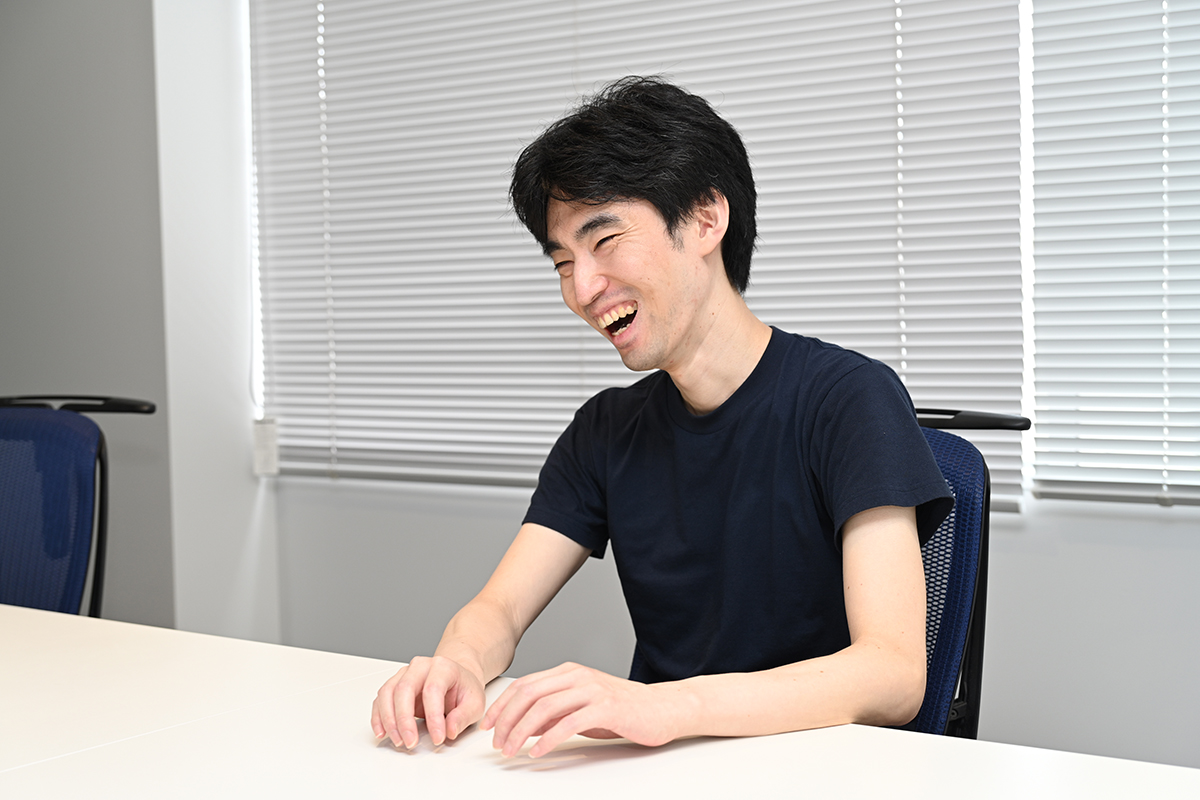
製品開発現場での経験も積みながら、専門性を高めていく
―バンダイナムコスタジオに入社を決めたのも、何か興味やきっかけがあったのでしょうか。
学生の頃、物理シミュレーションを研究していた時から、ゲームや映像といった人を楽しませる方向に技術を活かす仕事がしたいとは思っていました。
バンダイナムコスタジオでは様々なテイストやジャンルのゲームを開発しており、幅広い経験が出来るのではと興味を持ち、入社を決めましたね。
―入社後、どのような経緯で内製ゲームエンジン開発に関わるようになったのでしょうか。
新人研修が終わり、最初の部署配属がアニメーションの技術開発を行う部署でした。
そこで、自分が今まで研究してきた物理分野を活かしたいということを相談したところ、内製のクロスシミュレーション開発に携わることになりました。
当時そのアニメーション技術の研究開発を行っていた部署が内製ゲームエンジンの開発を行う部署と合流することになり、自分も一緒に携わるようになったという経緯です。
ただ、研究だけでなく、製品開発の現場も知っておかないといけないなと感じ始めたので、一度ゲーム開発プロジェクトの方にシフトさせていただいたこともありました。そちらが一区切りついたので、今はまたエンジン開発の方に戻っています。
―実際、ゲーム開発のプロジェクトに入ってみて良かったと感じましたか?
はい。良かったことの一つは、社内の様々なクリエイターと直接コミュニケーションを取ることができ、繋がりが作れたということです。
ゲーム開発ではもちろん仕様があってそれを実装していくのですが、その仕様を作った方に意図を確認するためのコミュニケーションを取ったり、実装後にチームの人たちと確認しあって調整をしたり…当たり前ではあるのですが、エンジニアに限らず他職種の方々とそういったやりとりや連携の経験が出来たのは良かったですね。
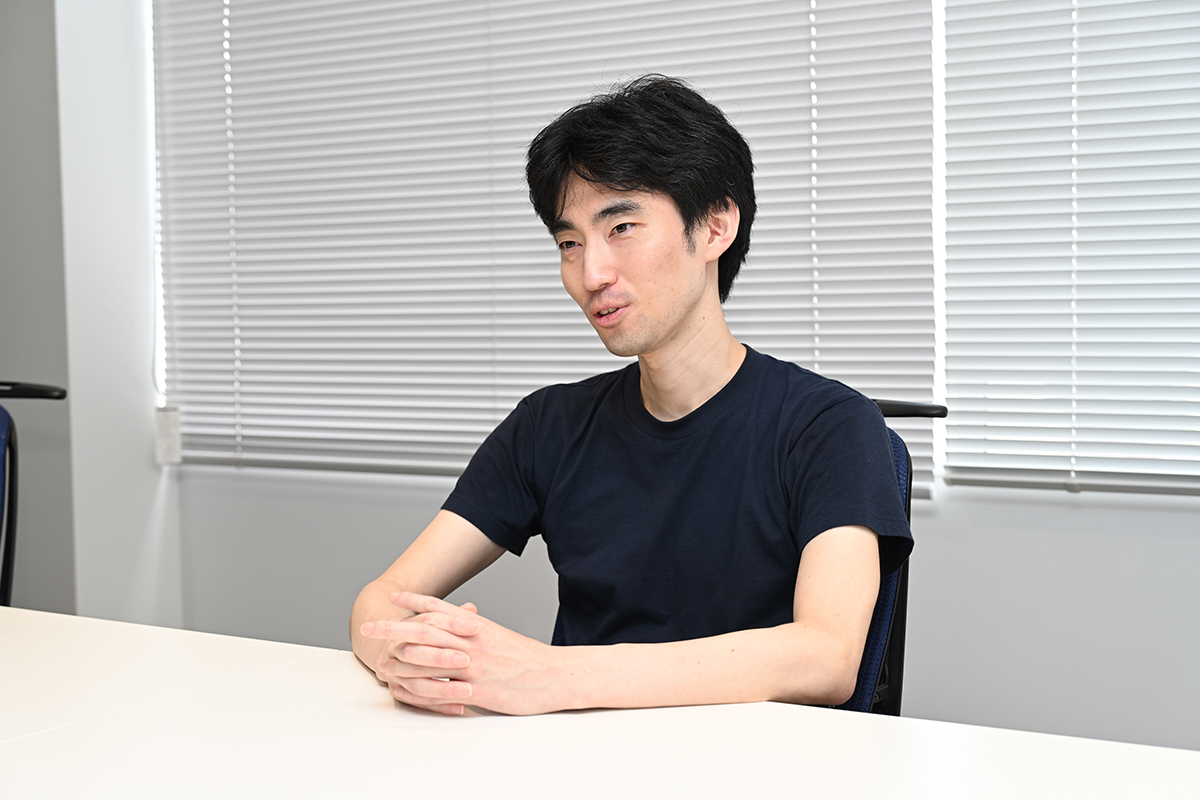
開発した技術が進化していく面白さ
―今までの仕事で一番印象深いものは何ですか?
クロスシミュレーションに関するエピソードをお話しさせていただきます。
クロスシミュレーションは、基本的にはキャラクターの衣装の動きをリアルに表現するために開発された技術です。ですが実際に使用していると、社内のビジュアルアーティスト* から「この技術はこれにも使えるのでは?」「あれにも使えるのでは?」と次々意見が出てきました。
例えば服以外ですと、髪の毛だったり、アクセサリー類であったり…。元は衣服のための技術でしたが、応用の幅が広がり、結果様々な部分に使用されることになりました。
中でも一番驚いたのが肌です。着地や何か物が当たった時のちょっとした肌の揺れや、脂肪が多く揺れやすいような太もも部分の肌にも使われました。自分自身が開発したものではありますが、想像もしなかった形で技術が進化し、とても面白かったです。
様々なバックグラウンドを持つ人と仕事をすると、思わぬ化学反応が起こるのだなと感じました。
* ビジュアルアーティスト:バンダイナムコスタジオでは、キャラクターアーティストや背景アーティスト等、アーティスト職の総称を「ビジュアルアーティスト」としております。
エンジニアに必要なものは技術力だけではない
―仕事を取り組むうえで大切にしていることは何でしょうか。
立場上、誰かからの依頼を受けて行う仕事が多いのですが、依頼があった際、「何をやりたいのか」「なぜやりたいのか」というのをまず理解することが重要かと思っています。
それらが出来ていると、依頼者の意思や熱意を自分に憑依させることが出来るというか…共感が生まれてモチベーションにも繋がり、結果的に良いものに仕上がると思っています。そういったものを原動力にして仕事を進めています。
依頼者の意図を上手く引き出したり、考えを汲み取ったりといったコミュニケーションも必要ですね。
―単純な技術力の高さだけではなく、そのような面も大事になってくるのですね。
また、「動くものを早く作る」という事も意識しています。
昔、上司に「目で見てもらった方が早い。特にビジュアルアーティストさんには文章ではなく、形にして見てもらった方が、お互いの認識が伝わりやすい」と教わったんですよね。確かにその通りでして。
実際に見てもらう事で、例えば「ここをもっとこうして欲しい」「実はこっちをイメージしていた」というような、表に出ていなかった考えや意図を言葉にしやすくするというのも、エンジニアには大切なことだと思っています。
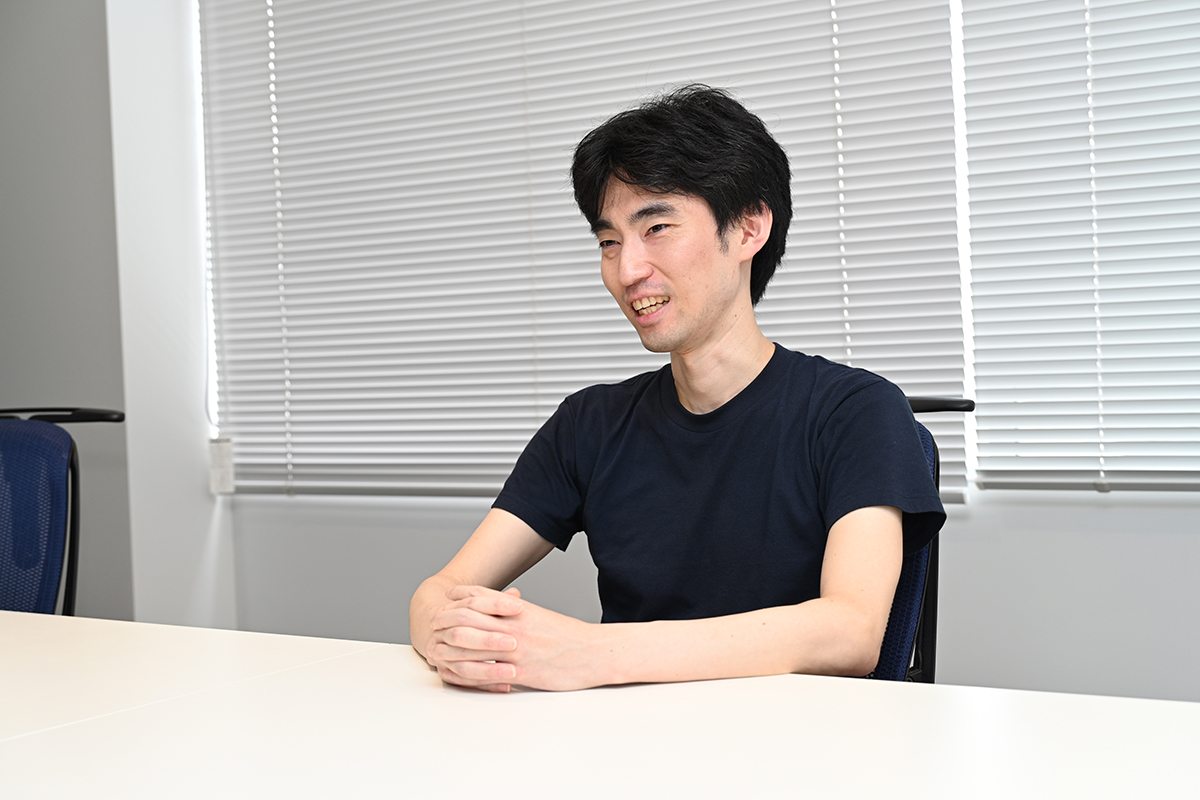
やりがいと今後の挑戦 ―“揺れ物”技術の第一人者として―
―実際に業務をされていて、やりがいを感じるのはどういう時でしょうか。
とてもシンプルなことではあるのですが、自分が携わったものが世界中、様々なデバイス上で動いていると思うと、不思議な気持ちになると同時に大きなやりがいを感じます。
例えば『鉄拳8』について、「衣装の挙動が良い」であったり「ロングヘアの揺れが美しかった」といった感想をネット上で見かけたことがありました。そういった声を見た時、自分の開発した技術がゲームのクオリティ向上に貢献できたんだ、と実感が沸いてとても嬉しくなりますね。
もちろん、これは自分一人の成果ではなく、ちゃんと綺麗に動くように揺れ方を調整したビジュアルアーティストの方々がいて、それらが組み合わさって今回の仕上がりになっているのですが、そういった嬉しいお言葉をいただけたことは、自分にとって大きな励みとなりました。
―今後チャレンジしてみたい事、抱負などはありますか?
内製クロスシミュレーションに関しては、内製ゲームエンジンに組み込むという事はもちろん計画されていまして、それは確実に遂行したいですね。内製ゲームエンジンに組み込まれ、様々なジャンルやテイストのゲーム開発で使われ、揉まれることによって、その技術をより進化させていきたいです。
ビジュアルアーティストからの要望もまだ多く残っていますし、自分自身『鉄拳8』のプレイ動画を拝見していてまだ出来ることがあるのではと思う場面もあるので、まずはそういったことに丁寧に向き合いながらより良いものを目指していこうと思います。
将来的には、「バンダイナムコスタジオの”揺れ物”技術はすごい!」と言われるようにしたいと思っています。
現在は他のアニメーション機能の開発に注力していることが多いのですが、いずれは”揺れ物”挙動の第一人者として活躍していきたいと考えています。
―ありがとうございました!
TEKKEN™8 & ©Bandai Namco Entertainment Inc.





