※以降の文中では、バンダイナムコスタジオをBNSと省略表記を用います。

テクニカルアーティスト 柳谷 太一
マルチな活動から『何でも屋』へ
―お時間いただきありがとうございます!まずは現在の所属と業務内容を教えていただけますか?
TECチームに所属しています。プロジェクトでは『何でも屋』をしているような感じです。
例えば相談を受けたら、「こうしませんか?」という提案をしたり、解決をしたりする仕事ですね。その相談の過程で「では、ツールを作りましょう!」であったり、人と人をつないで折衷案を見つけたり、時にはツールの使用ルールを決めたりする…ような仕事がメインとなっています。
―本当に『何でも』するのですね。どうやって業務の相談を受けるのでしょうか?
対面もメールもありますが、チャットでも相談を受けています。
プロジェクトの相談とは別に、部署として社内全体の開発環境構築の相談を受けることもありますし、特定製品の質問を受けたり、最新情報共有・発信などでもチャットツールを活用したりしています。
―柳谷さんがテクニカルアーティストを志したきっかけを教えてください。
実は就職活動をはじめるまでテクニカルアーティストという職種は知らなかったんですよね。
就職活動をはじめて、いろいろな企業の応募サイトを観て、そこではじめてテクニカルアーティストという横文字を見たんです。で、これは何だ?と。(笑)
それでBNSの応募サイトのテクニカルアーティスト募集要項を読んでみたら、今まで自分がやってきたことや、BNSが求めていることから、「あれ? これ自分のことを書いているんじゃないか?」と思いまして。それがきっかけですね。
テクニカルアーティストのことをいろいろ調べてみると、ますます今までやってきたことが仕事になるのではないか、自分がやりたいことがここにあるんじゃないか、と思ったわけです。正直見つけたときは「天職」だと思いました。
―学生時代どんな勉強をされていたのでしょうか?
理工学系の学科・研究室で三次元映像の研究室に所属していました。研究室のメンバーには映像業界ではなく、ゲーム業界へ行く人もいたので、それをきっかけにゲーム業界を目指しました。
プライベートで単純にCGが好きだったので、大学に入ってから独学で始めました。あとは音楽も好きでDTMも始め、イラスト制作、アニメーション制作をしていたら、いろんなパーツが揃ったので、それで自分で動画を作ったり、ゲームを作ったりというのを「自分1人監督」としてやっていた大学生活でした。
―とてもマルチですね! 音楽も絵もご自分でやっていたのでしたら、職務としてテクニカルアーティストを選んでいなかった可能性もありますか?
その可能性はあったと思います。大学から大学院に進学するか就職するかという選択肢のうちに、このまま進学するよりかは、例えばCGの専門学校へ行って、それから業界に行くか?という考えもあったりしたので、もしかしたらCGデザイナーになっていたかもしれないです。

―入社時のエピソードなどを教えてください。
BNSの面接は確か3~4社目くらいでした。いろいろな人と話して、他の会社の方と面接もしてきたのですが、BNSの面接は緊張しなくてよいように、リラックスできる雰囲気を作っているな、ということを感じたのを覚えています。もちろん緊張はするんですけど(笑)
―面接官とどんな話をしたか覚えていますか?
大学の研究の話と趣味でCGとアニメーションをしていた話はしましたね。面白かったのが海外勤務のエピソードでした。「海外にもスタジオがあるけど興味はありますか」という質問に対して、「日本食が恋しくなるんでちょっと……」みたいな回答をした記憶があります。そういうことが言える雰囲気の面接でした。
テクニカルアーティストに必要な考え方
―テクニカルアーティストとはどんな仕事ですか?これから目指す方にもわかるように、ご説明いただけますでしょうか。
さまざまな分野があって、それを文章的にくくる言葉として「テクニカルアーティスト」があるようなイメージです。人によってはリギングが得意な方、プログラムができる方、ツールを作れる方もいれば、ライティングができる人もいます。ですので、これができればテクニカルアーティストです、という風に一概に言えない職務ですね。
全体のワークフローを俯瞰して見て、より合理的な判断のもと効率化を図っていく、アーティストとエンジニアの橋渡しをするのが「一般的に言われている」テクニカルアーティストの仕事です。
橋渡しをする中で、人の間に入って伝える言葉を選び、落としどころを探します。また、目先の問題解決だけでなく、この後どうなるのか、という先まで見越して効率化を図ったり、ルールを敷いたりすることもあります。
―こういうスキル・人格はテクニカルアーティストに向いている、などの考えはありますか?
「常に疑問を持っている人」は向いていると思います。何かを教わったとして、それを鵜呑みにして思考停止でなくて、「じゃあそれはなぜ?」という疑問を持ち続けることはとても大事だと思います。
あとは相手の気持ちに共感できることも大事ですね。常にその受け取り手側の目線に立って、もしも自分がこうした時に、じゃあ受け取り手がそれを見た時にどう感じるか、というところを自分の中でシミュレーションできて、さらに自分で評価できるというのはとても価値があると思います。
要するに、「思いやり」があればいいかもしれません。ちゃんと疑問を持って、思いやりを持てればいいと思います。
―もしBNSのテクニカルアーティストになりたい、と希望されている方がいるとしたら、どんなアドバイスをしますか?
何をしておけば有利かよく聞かれますが、「今しかできないことをやってほしい」と言いたいです。就職がゴールではないので。これができるからBNSに入れる、というわけではないので、武器となる経験、手札を学生のうちに増やしておいてほしいと思います。
例えば社会人になると時間がなくなるので、「海外に行く」というのもいい経験になると思います。あとは、完璧でなくてもいいので、最新の技術をつまんで触ってみる、でもいいと思います。「自分はこれで戦える」というものを身に着けてほしいです。
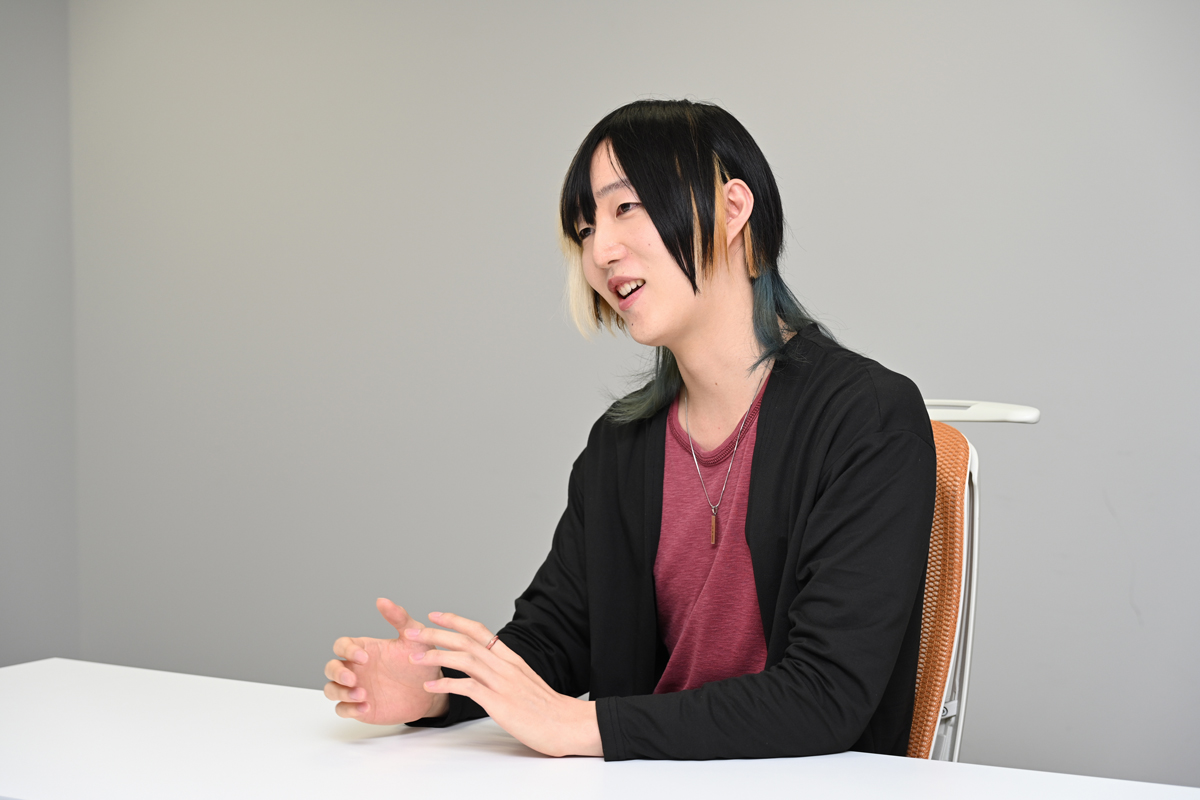
―仕事に取り組む上で大切にしている自分のルールというのはありますか?
先程のテクニカルアーティストのスキルのときも話しましたが、「思考を停止しない」「常に疑問を持つ」、「相手がどう思うか」の3つを大切にしています。
目の前のことだけ問題解決して根本が解決されていないことがよくあるんですよね。その根本の問題を解決するために、じゃあどうすればいいか、という考えを持つところは大切にしているので、思考を停止しないよう意識しています。
やりがいと今後のチャレンジ
―やりがいを感じるのはどんな時でしょうか?
やり取りする人からから直接感謝される、というところはやはりやりがいになっています。
「何か進展すれば」と思ってみなさん相談してくれているので、それに対してしっかり答えが出せて、それに対して信頼が生まれて、感謝されるというサイクルにもやりがいを感じています。あとは「この人に相談すれば、解決はしなくても何か進展するかもしれない」と思って連絡をくださったり、自分をそういう風に思ってもらえているというところも、最近はやりがいになっているなと思っています。
―どんな人が相手だと働きやすいと思いますか?
「相談してくれる人」がいいですね。
自分たちが仕事で全てを先回りして動くのは不可能で、みなさんからいただく相談や要望ベースになりがちです。その要望があったことをまず我々に相談してくれないと、チームとしても動けないことになってしまいます。
気合いでなんとかしようとする方は多いと思うのですが、直接でもチャットでも構わないので、まず相談してくださる方とは仕事がしやすいと思います。「ちょっとめんどくさいんですけど、ここに困ってて…」みたいな内容でも構いません。
―今後チャレンジしてみたいこと、抱負などはありますか?
新卒のテクニカルアーティストを増やせたらいいなと思っています。他の職種に比べて少ない気がしています。他の会社のテクニカルアーティストとつながりがあるので、例えばこのインタビューもそうなのですが、何か活動ができたらいいな、と。
テクニカルアーティストが業界に増えると、自社も他社も負担が減って、より開発に集中できると思うので。
―座右の銘はありますか?
今の自分の考えに似ているな、という意味で「春風秋霜(しゅんぷうしゅうそう)」という言葉がぴったりきそうです。
意味は簡単に言うと「人には優しく、自分には厳しく」というものです。
―ありがとうございました!





