
背景モデラー 齊藤 達也
趣味から始まった、3DCGで風景を描く事への憧れ
―まずは現在の所属と業務内容を教えてください
現在、アートスタジオのTA(テクニカルアーティスト)課に所属しています。
入社当初は背景モデラーとしてキャリアをスタートしました。
背景制作を進める中で、プロジェクトの仕様に合わせてアセットを変換するツールの開発や、プロシージャル技術を活用した表現力の向上、効率的なアセット制作環境の整備などにも取り組むようになり、そうした開発の中での工夫の積み重ねの結果、TA課に所属することとなりました。
所属はTA課ですが、プロジェクト作業の中では背景モデラーとしての業務も続けており、今でもそちらがメイン業務となります。
背景モデラーの業務としては、ステージ制作やアセットの発注・監修などがあり、技術とアートの両面から、より良いゲーム体験を支えることを意識して業務に取り組んでいます。
―以前からCGなどの専門的な分野を学ばれていたのでしょうか?
元々は、ゲームやCGとはまったく縁のない仕事に就いていましたが、趣味を突き詰める中で関心を持つようになりました。
私の趣味は風景画を描くことと、旅先での街歩きです。街を歩きながら気になる建物や風景を観察し、写真を撮ったりスケッチをしたりするのが日課でした。
絵作りの技術を向上させたいと思い、ゲーム・映像業界のアーティストの作品が集まるポートフォリオサイトを参考にするうちに、3DCGで風景を作ることに興味を持つようになりました。
入社の数年前からは、仕事の傍ら専門学校の休日授業に通い、3DCGの基礎を学び始めました。
特に扱いやすいゲームエンジンに触れるようになってからは、自分で作った空間を自由に歩き回り、その場の雰囲気を体感できることに大きな魅力を感じましたね。
こうした経験を通じて、「3DCGで風景を作る仕事がしたい」という思いが強まり、背景モデラーを目指すようになりました。
現在はアクションゲームの背景制作を中心に担当しています。

「決まっていないデザイン」をどう作る?架空の世界のリアリティとは
―今までの仕事で一番印象深いものは何ですか?
デザイン作業に戸惑いながらも取り組んだことで、背景モデラーとしての視野が広がった経験が印象に残っています。
現在携わっているプロジェクトでは、さまざまな風景やオブジェクトの制作を担当しています。
仕事に就く前は、設計図のようなものが事前に用意されていて、それを忠実に再現するのが背景モデラーの役割だと思っていました。しかし実際には、具体的なデザインが決まっていないケースもあり、空間の構成やアセットのデザインを自分の裁量で考えながら進める場面もありました。
プロジェクトによって状況は異なると思いますが、私にとって非常に貴重な経験でしたね。
デザインの経験が少なかったこともあり、最初は苦労しましたが、作品世界をより魅力的に描くためにはどうすればよいかを考える力が身につき、アートコンセプトに沿った背景を構築できるようになりました。
また、アセットの監修業務では、他のビジュアルアーティストに自分の意図を言葉で伝える必要があります。デザインを考える過程をしっかり学んだことで、チーム内でのコミュニケーションにも良い影響があったと感じています。
―実際、どういった考えやこだわりを持って背景デザインをするようになったのでしょうか?
架空の世界を描くことが多いため、絵作りやアセット制作では、その世界にリアリティを感じてもらえるよう常に意識しています。
たとえば都市や集落など、人工的な空間を作る際には、「なぜそこに街ができたのか」「どんな人が、どのように暮らしているのか」といった背景を想像しながら絵作りを進めています。そうすることで、単なる装飾ではなく、生活の気配が感じられる空間に仕上げることができます。
また、実在しない鉱物などのアセットを作る場合でも、「どうやってその鉱物が成長するのか」「どんな環境で形成されるのか」といった自然のメカニズムをイメージすることで、そのアセットなりのリアリティを生み出せると感じています。
私は博物館に行くのが好きで、歴史・民俗系から自然科学の展示まで幅広く興味を持って観ています。こうした体験は、モノのデザインを考える際や、空間に物語性を持たせるうえで大いに役立っていますね。
―そういった部分にも、興味や趣味が活かされているのですね。
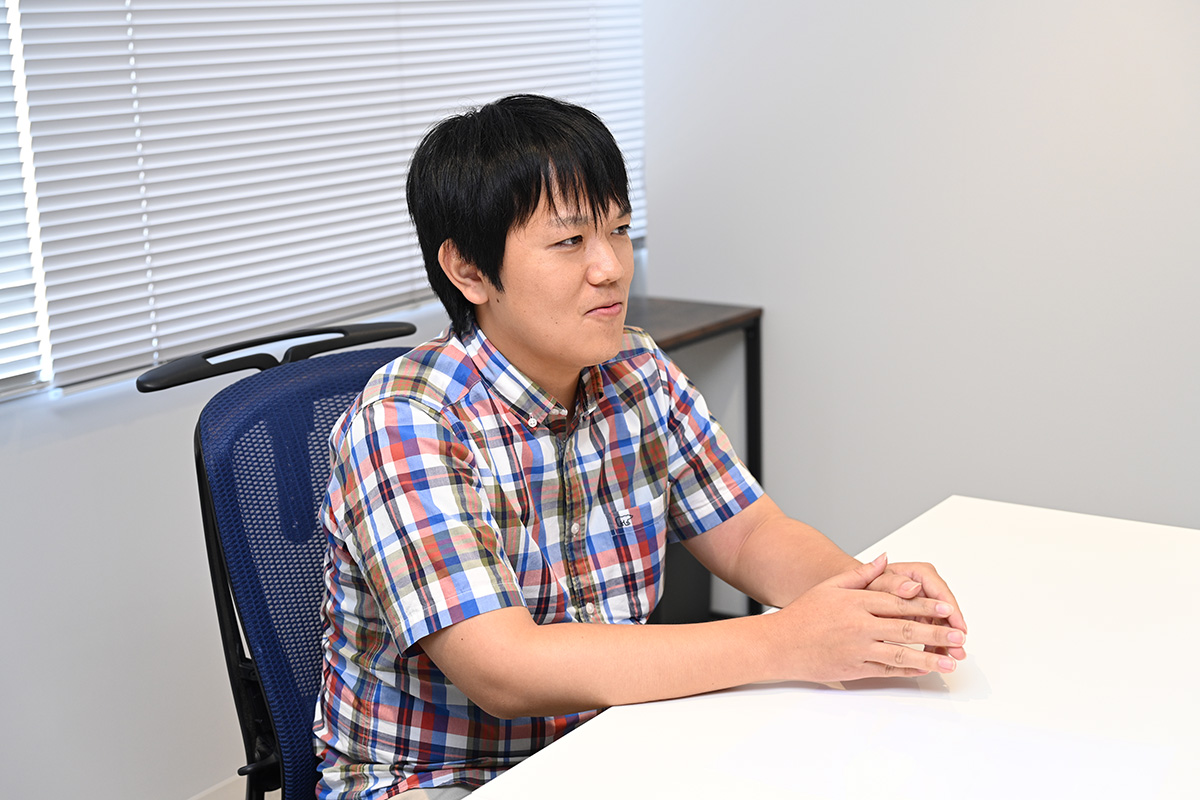
“共に創る”ことで広がる表現の可能性
―実際に業務をされていて、やりがいを感じるのはどういう時でしょうか。
さまざまな職種のメンバーと協力して、ひとつのものを作り上げられたときに、特にやりがいを感じます。
なかでも印象に残っているのは、ゲーム内でプレイヤーが破壊できるギミックの制作に関わったときのことです。
仕組みをどうするかといった検討から、最終的なビジュアルの完成まで、一貫して携わることができた案件でした。破壊の仕組みや演出については、エンジニアやエフェクト、サウンドなど各専門チームと連携しながら、負荷やリアリティ、質感などを細部まで調整しました。目標とする表現に向けて計画的に進めながらも、試作や議論の中でさまざまな提案をいただき、建設的なやり取りを重ねてクオリティを高めることができたと感じています。
最終的には、自分が当初思い描いていた以上に魅力的なものに仕上がり、大きな達成感とやりがいを得ることが出来ましたね。
―最後に、バンダイナムコスタジオのバリュー(Grow BNS:挑戦・自律・追求・共創)の中で、特に意識しているものや、日々の業務で大切にしている考え方などを教えてください。
私が特に意識しているのは「共創」です。
背景制作は多くの職種と関わる仕事であり、目的を共有しながら、それぞれの専門性を活かして進めることが求められます。自分の知識や技術だけでは届かない部分も、他職種の視点や工夫によって補われ、より完成度の高い表現につながります。日々の業務では、互いの立場や考え方を尊重し、丁寧にすり合わせながら制作を進めることを大切にしています。
―ありがとうございました!






