※記事内ではコロナ禍でのテレワーク勤務に関する記載がございますが、現在特例措置は終了しております。なお、育児や介護等の事情によるテレワーク配慮措置は行っております。

ナラティブディレクター 糸見 功輔
所属と業務内容
— 本日はお話を伺うのを楽しみにしていました! 早速ですが、現在の所属や業務内容を教えてください。
神戸芸術工科大学 視覚情報デザイン学科を卒業して1998年に旧ナムコに新卒で入社しました。
入社当時は2Dデザインや映像編集を担当していましたが、映像ディレクション、アートディレクションを経て、『ACE COMBAT』シリーズでは、ナラティブディレクターとして、ゲーム内の演出全般の監修や、トレイラー制作を担当しています。
— 趣味や興味関心がゲーム開発に結びついたことはありますか?
学生時代はバンドをやっていました。当時はバンドブームで、友人とCDを貸し借りしたり、暇があればレコードショップに通って視聴を繰り返して、いろいろな音楽に触れていましたね。最初は邦楽ロックから始まって洋楽に移って、メタル、ブルース、カントリーミュージックまで。
浪人から大学時代にかけては、映画鑑賞に時間を費やしていました。ヒット作から、モノクロ映画、アニメ、時代劇、西部劇、Vシネ、B級ホラーまで、映画館にも通い詰めて、レンタルビデオ店でも借りるものがなくなるくらい観ました。
何かひとつ気に入ると、その監督が影響を受けた作品や、バンドの音楽的なルーツまで知りたくなって、どんどん深堀りしていました。ただ、しばらくすると満足してしまうんですよ。また、他の面白そうなものに気持ちが移って、またどっぷりと深掘りしていくようなことを繰り返していました。凝り性にみえて飽き性なんです。
だから、僕は一つのものをずっと追いかけているということが無いですね。とても雑多です。
ただ、仕事にはこの雑多な趣味が役に立っています。例えば、ゲームの演出コンセプトや方向性が定まった後も、開発はすんなり進むことはなく、予算やスケジュール、技術的な問題を乗り越えたうえで、演出手法を考えなければいけません。課題が山積みです。これを解決していくには自身のストックが重要だと思っています。過去にストックしたアイデアをどう組み合わせていくかが肝になります。
■これまで関わった主なタイトル
ACE COMBAT 3 electrosphere 2Dワーク/映像制作
RIGDE RACER V 映像ディレクター
7(セブン) ~モールモースの騎兵隊~ シネマティックディレクター/ムービー制作
ACE COMBAT 04 Shattered Skies インゲームシネマティックディレクター/演出補
Venus & Braves ~魔女と女神と滅びの予言~ シネマティックディレクター/ムービー制作
ACE COMBAT 5 THE UNSUNG WAR シネマティックディレクター
ACE COMBAT ZERO THE BELKAN WAR アートディレクター/ストーリー/総合演出
ACE COMBAT ASSAULT HORIZON ビジュアルアートディレクター/総合演出
FRAGILE ~さよなら月の廃墟~ 絵コンテ/カットアウトアニメーション作成
ACE COMBAT INFINITY アートディレクター/ストーリー/総合演出
ACE COMBAT 7 SKIES UNKNOWN ナラティブディレクター
— どのようにアイデアのストックを貯めていますか?
昔見ていた映画でいうと、低予算映画は手法の試行錯誤が面白く、それが現在の演出手法のストックにもなっています。音楽もそうですね。音と映像の組み合わせ方は色々な手法があるので、格好いいと思った瞬間は逃さないようにしています。最近は忙しくて映画も多くは観られていませんが、例えば、資料ストックであれば旅系YouTubeをよく観ます。
よく観るYouTubeチャンネルは、20代のバックパッカーが海外をローカルな交通手段で周り、その都度、その土地の人や文化と等身大で触れ合いながら旅をするという内容です。これがとても新鮮でした。特に演出も加えられていないので、生活感がリアルに伝わってきます。なかなか知れないことなので、とても興味深いです。
— 確かにそうですね。
アメリカなどの大都市はなんとなく想像がつくのですが、例えば南米の山奥となると知らないことばかりです。そこに住む人がどういう生活をしているのか、どんな人柄なのか、普段どんな料理を食べているのか、観ているだけですごく楽しいです。あとで、山奥の田舎のイメージが必要になったときに、「あの動画でロバ引いていたおばあちゃんがいたな」ともう1回調べ直したりできるので、自分自身の強い情報源になっています。
— いまの時代ならではの方法ですね! そんな中、過去のストックに助けられた経験はありますか?
企画開始の時点で1年後発売と決まっていたタイトルの開発ですね。『ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WAR(以後、ACE COMBAT ZERO)』というタイトルです。
とにかく人も時間もないプロジェクトでした。
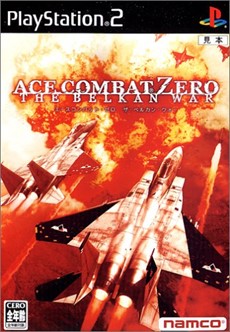
THE BELKAN WAR
— 今だと1年では考えられないですよね?
考えられないですよ。
前作の『ACE COMBAT 5』のモデルアセットを再利用できる部分もあったのですが、ストーリーなどは新しく作る必要がありました。まずは、ディレクターと2人で「今作は敵エースがいっぱい出てくる決闘のような空戦をやりましょう」というのを決めました。
その後、とりあえず脚本を書ける方を探さなきゃいけなかったのですが、本当に時間がないので、ベースのストーリーは僕が書きました。3日くらいで。
— 3日で書いたんですか?
自分の持っているストックをフル活用して。勢いだけの殴り書きみたいな状態のものでしたが、ディレクターや関係者に読んでもらって手応えを感じました。
そこから、何人かで手分けして精査していったのですが、お話の筋や、キャラクターの人物像、世界観設定は、最初に書いたものから変わって無いです。
— 糸見さんのストックが詰まっているんですね。
新しく調べている余裕もあまりなかったこともあって、その時に好きだったものや、昔好きだったものを全部詰め込みました。
劇中のムービーに関しては、時間や予算の問題もあったのですが、コンセプトを実現するには実在の人物が必要だと考えて、実写映像に挑戦しました。でも、周りからは超反対されたんですよね。

— それは時間がないから反対されたんですか?
2006年ごろの話なのですが、当時は「実写を使ったゲームは当たらない」と言われていました。
すでに、実写を使用したゲームはあったのですが、まだまだ「ゲームなのに実写なんて」みたいな風潮がありました。「実写だと売れない」とも言われたのですが、僕としては、いけるだろうという感触はあったんですよね。それは「証言VTR」という手法です。
— 証言VTR!?
はい、テレビとかでよく見るインタビュー映像ですね。
ドキュメンタリー番組のインタビューで、英語で喋っている上に吹き替え音声を乗せるような映像があるじゃないですか。それを再現することにしました。
「ゲームの舞台となっている戦争は過去のもので、もう終わっている。戦後に消えた噂のエースパイロットがプレイヤーで、インタビュアーがプレイヤーの人物像を探るために、当時の関係者に話を聞く」という設定にしました。
インタビュー映像ならば、みんなが見慣れているはずなので、実写でも違和感はないだろうというのが理由です。その代わり、背景はCGで作り、世界観を伝えていくという方針で進めました。CGではなくリアルな人物が話すことで、インタビュー映像にも説得力を持たせたかったのです。カメラは固定カメラのみで撮影。これで編集作業も削減できました。
あと、BGMは今までのシリーズから少し外して、フラメンコ調のスパニッシュギターを取り入れました。これも反対されました (笑)。
— 『ACE COMBAT』というと、ロックのギターとか、オーケストラや映画音楽っぽい、壮大な感じの音楽でしたよね?
前作が大作映画のようなコンセプトとボリュームだったのですが、ZEROでは、もう少し個人的な戦いにフォーカスさせたかったんです。そこで、孤独な乾いた戦いをイメージできるよう、枯れた音のするスパニッシュギターやフラメンコ調の要素を入れたいとサウンドディレクターに話しました。
「戦闘機と合わない」という意見もあったのですが、今回は決闘がモチーフと決めていたので、決闘と言えば西部劇。戦闘機でマカロニエスタンをやってしまおうという意図もありました。西部劇も大好きでよく観ていたのでこれもストックですね。
作曲の小林啓樹さんがこちらの意図を汲んで素晴らしい曲を作り上げてくれました。テーマ曲の『ZERO』は今ではACE COMBATシリーズの中でもトップの人気曲になってくれたので、本当によかったと思っています。
全ての工程で苦労はしたんですけど、楽しかったですね。ゴールを決めたら、頭の中のストックを引っ張り出して繋ぎ合わせながら突っ走るような感じでした。

ナラティブディレクターについて
— ナラティブディレクターという肩書きについてお話を伺えないでしょうか。
ゲームの演出全般、音楽、映像、ストーリーをゲーム中のテンポ感等も含めて管理する役割です。総合演出とか演出監督みたいな立場です。
ACE COMBATは、ドラマティックな要素を強調するゲームなので、演出のコントロールがすごく難しいんですよね。そして、ロールプレイングゲームではなく、あくまでもシューティングゲームなんです。なので、止まってゆっくり会話が進むことはありません。常に飛び続けている中でストーリーが展開していきます。
シューティングの部分はゲームデザインディレクターが担当していて、自由に飛び回れる戦闘機の遊びの部分を担保しながら、物語を含めた体験をどうやって盛り上げていくかを考えるのが演出監督の役割です。
長く演出を担当しているのですが、演出監督に相当する呼び名が難しくて、英語に訳すと「ディレクター」になっちゃうんですよ。
— これだと糸見さんの担当領域が伝わらないですよね。
はい。ある時、プロジェクトメンバーに、「海外では、ナラティブディレクターという役職が一般的になりつつあるので、これが当てはまるんじゃないですか」と提案頂いて、それ良いですね、となったのが最初です。それからナラティブディレクターを名乗らせていただくようになりました。
— 海外では一般的っていうのは、映画業界などですか?
ゲーム業界でも、「ナラティブ」という用語は一般的になっています。直訳すると「物語」ですね。
海外のグループ会社のスタッフと話した時も、「ナラティブディレクターっているの?いないの?」みたいな話題があがりました。海外では専任での採用もあるようです。
きっと、ゲームの表現方法がより細やかになったことが理由だと思います。例えば、以前はキャラクターが出てきてセリフがテキスト表示されていれば、会話をしている表現となっていたのですが、解像感が上がった今ではそういうわけにいかない。表現力が上がれば上がるほど画面に違和感が出てきてしまいます。違和感は没入を妨げます。
ゲーム内のあらゆるところで没入感を削がないように演出を決めなくてはならないので、ナラティブデザインを設計できる人、物語を体験として落とし込める人が各チームに必要になってきます。
— 後輩育成も考えているのでしょうか?
後輩育成とまではいかないですが、技術研究の一環として、社内でナラティブデザインのコミュニティを立ち上げています。
ナラティブデザイン研究として、ゲームUXのフレームワークに則って、「どうやってゲームの世界に没入してもらえるのか」を分析する会を週1回のペースで開催しています。毎回の参加者は20名くらいです。
そんなに難しい話ではなく、感動したゲーム、面白いと思ったゲームの話を教えてもらって、それ何が面白いんだろうね、なるほど、こういうことをやっているから面白いのか、というのをみんなで話し合っていく会です。他には、キャラクターに感情移入する方法などテーマを決めてディスカッションしたりもします。
まだまだ、僕も勉強させていただいています。
— 面白そうですね! クリエイター以外の人も参加できますか?
はい、一昨年は法務担当の方も参加されていました。社員であれば自由参加で、常に募集しています。開発だけでなく、色々な人の感動ポイントも知りたいです。
テレワーク勤務もあり、プロジェクト以外の人と話す機会がなかなかない中で、若い社員や、キャリア採用で入ってきた方々にとっても、良いコミュニケーションの場になっているのではないでしょうか。
こういった場があると、みんなの知見を共有しやすいのと、プロジェクトを超えて、演出に関わる課題や、解決方法などを話し合えるので、コミュニティの活性化にはすごくいいなと思っています。
— そういうコミュニティが活かせるのであればすごくいいですよね。
立ち上げて本当に良かったなと思いますね。これで何にも役に立たなかったら、悲しいですが(笑)。 おそらくこの活動の効果が現れていくのは、さらに2,3年後とかになるのだと思います。
単純に知識を持って帰るのではなくて、ここで築かれた関係性を持って帰ってほしいなと思っているところもあるんですよね。困った時にあの人のところを聞きに行こうとか。

— 開発の仕様としてはこれが正しいけれども、絶対こうやった方がよくなるってなった時、糸見さんならどう解決しますか?
僕なら、映像にして見せます。その方が自分の考えがスムーズに伝わると思います。
感覚の問題って難しいです。言葉で伝えても解らないものってありますよね。品質は低くても最終イメージに近いものを見ることで、何が良いか悪いか、共通認識を持つことができます。
あと、映像の場合、数秒、数フレームのタイミングの違いでイメージが全く変わってしまうことがあって、少しのコントロールで格段に良くなることがあります。じゃあこれを言葉で説明できるかと言われると、なかなか難しいんですよね。やっぱり伝えづらいところは映像化するのが一番いいのかなと思っています。
— きっと映像を学んできて、音楽もデザインもできる糸見さんだからこそ、伝わる方法なのかもしれませんね。
そういう意味では今のポジションが僕には一番合っていると思っています。
今後のチャレンジ
— いろんな経験を積み重ねてきた糸見さんですが、今後チャレンジしてみたいことと抱負はありますか?
ゲームを出発点としてもっといろんなジャンルにも挑戦したいですね。汗とか涙とか笑いとか自然と出てしまうゲームを作ってみたいです。
あとは新しい表現を試していきたいですね。表現として新しいことにチャレンジできるかどうかに興味があります。
— チャレンジングなものであればあるほど、ちょっと糸見さんの心が躍りますか?
むしろ、辛くなります(笑)。辛いけど、やらなきゃいけなくなったからスイッチが入る感じですね。そして、結果的に成長もできる。
ずっと得意分野だけでやっていると全部手癖になっちゃうんです。今までの経験でなんとなくできちゃうので、とりあえずやれることで終わらせてしまいがちです。
なので、逆に「これは困った」「これはまずい」「これは後に引けない」ということがない限り、自分の中の成長もなければ心躍ることもないですね。
本来は面倒くさがりなので、やりたくないという気持ちはすごく強いくせに、それをやらないと自分は楽しくないという変な矛盾を孕んでいるんです。結局大変な方へ踏み込んでいかないと自分は動かないというのを自覚しているところです。
— 壮大なゲームの世界観の裏には、糸見さんの経験の蓄積があったんですね! いろいろとお話いただきありがとうございました!
©Bandai Namco Entertainment Inc.





