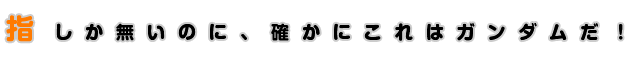『VR ZONE Project i Can』ができるまで(前編)に引き続き、今回も「VR ZONE Project i Can」の開発エピソードをお届けします。
今回は、VR特有の『3D酔い』を軽減するノウハウや、アーケードゲーム筐体を作り続けてきたノウハウなど、世界初のVR施設を開発するまでのエピソードを、コンテンツの話とともにご紹介いたします。
*前編の内容はこちらから>>>「VR ZONE Project i Can」ができるまで(前編)
■大森: 『スキーロデオ』では、吐いた息が白くなるのでいきなり引き込まれました。それだけでもゲレンデの雰囲気を強く感じました。

■大森 靖(おおもりやすし)
インタビュアー
バンダイナムコスタジオ 執行役員
●石井嘉: プレイヤーの呼吸をマイクで感知して、映像に出す仕組みです。その演出のためだけにマイクが付いています。
■大森: 芸が細かいなあと思いました。(笑)でも素晴らしいアイディアですよ。
●石井嘉: 吐いた息が白い演出は、実はちょっとした遊びのつもりで入れておいた仕掛けです。最初はプレイヤーの呼吸とは関係なく、白い吐息の演出を入れていたのですが、それを目にした田宮さんがすごくビックリされまして。
●田宮: これは効果的な演出だと思いました。すぐさま、呼吸に連動できないかと要望して、マイクを追加することにしました。
●石井嘉: SNSなどで「吐く息が白くて驚いた」というような書き込みが多かったようで、結果大成功でした。

『スキーロデオ』
■大森: 滑り出す前に、斜面がけっこう急なので、気持ち落ち着かせるために「はーっ」と息を吐くのですよね。その息が白いのだから、衝撃的でした。
●福冨:相乗効果と言いますか、肌で感じられる風がとても冷たかったという感想も多いです。実際の温度は冷たいわけではないのですが、そう思わせるだけのチカラが白い息の演出にあるのだと思います。
■大森: その通りですね。ゲレンデ特有の、ピーンと張り詰めた空気を感じました。それから、滑り出してみると、足元からもスキーを滑っている感触がきちんと伝わってくるところもアピールポイントだと思います。
●白井: 足元の振動は後から追加しました。元々大きめの振動は入っていたのですが、途中で「スキー板のエッジを立てて滑った時のガリガリ感もあるといいよね」という話が出まして、細かい振動が出るように体感音響振動の機構を追加しています。
●石井嘉: 開発当初の『スキーロデオ』はプレイ中の酔いが酷いという大きな問題がありまして、その対策を何とかしなければなりませんでした。酔いが軽減されるようになったのは、筐体がしっかり可動するようになってからですね。
■大森: つまり、可動筐体は酔いにくい?

●石井 嘉明(いしい よしあき)
ソフトエンジニア
『スキーロデオ』を担当
●石井嘉: その通りです。視覚から入ってくる情報に対して、自分の経験から想起される音と振動が足りない事も酔いに繋がります。
●柿沢: 自身はその場に留まっているのに、VRの中で移動するようなコンテンツだと酔います。特にピッチング(上下の動き)がキツい。自分は動かないのに映像だけで上下動を表現すると数秒で酔ってしまいます。
●石井嘉: 筐体が可動するようになってからも、最初は筐体と映像の上下動のシンクロ度合いが足りていなかったせいで、酔いが残りましたね。開発中はとにかく酔いとの戦いで、「今日は電車に乗って帰れないかも」と思う事が何度もありました。
●柿沢: いわゆる『3D酔い』は、2006年に発売された『機動戦士ガンダム 戦場の絆』※7の頃から起きていた課題です。この製品を開発していた時から10年以上もの間、BNSでは酔いの軽減に関する研究を重ねてきましたので、多くのノウハウが蓄積されています。今回開発したVRコンテンツにも、そのノウハウが随所に生かされています。
■大森: 『マックスボルテージ』はあの中でも少し毛色が違う印象です。その印象の割には、後から入ってきたコンテンツとしては非常に良いポジションに収まっていたと思います。開発開始時期も後発だったのでしょうか。
●田宮: 全てのコンテンツが、期間内に仕上がるようスケジューリングしていましたが、開発の進捗状況が読めなかったので、出展ラインナップのプランを複数立てておきました。『装甲騎兵ボトムズ』と『マックスボルテージ』はそのプランの1つに沿った出展タイミングということになります。
■大森: 開発自体は順調だったのですね。とは言え、何か苦心したところもあったでしょう。
●白井: VRゴーグルを付けたまま防音室内を歩き回るため、安全性の確保が課題でした。具体的に言うと、VRゴーグルから出ているケーブルの取り回しをどうするか、ですね。そこはケーブル巻取り機を使い余分なケーブルを巻き取ることで解決しています。

『マックスボルテージ』
●福冨: ケーブルの巻取り方にもひと工夫ありまして、VRゴーグルから直接巻取り機につながっていると、後ろに引っ張られる感覚が強まってしまいますので、その感覚を和らげるための仕掛けを追加しています。
■大森: 実はケーブルをやんわりと引っ張られていたのですか。それは全く気が付きませんでした。いや、言われなければ誰も気づかないと思いますよ。プレイヤーがケーブルに絡まった事例はあるのですか?
●田宮: そういえば、聞いたことがありませんね。全く問題無かったのだと思います。
■大森: 今後はプレイヤーが自由に動き回れるVRコンテンツも増えるでしょうから、この経験と技術は非常に役立ちますね。
『マックスボルテージ』といえば防音室も特徴的です。それについても話していただきましょうか。
●田宮: VRコンテンツは没入感を高めるために、基本的にはヘッドホンを付けて楽しむものだと思っていましたので、『マックスボルテージ』についても最初はそのつもりでした。
しかし、BNSのディレクターとサウンドの担当者から、「音圧を体感させたほうが良いのでは?」と提案がありまして。比較……するまでもなかったのですが、ヘッドホンよりも全身で音圧を感じることのほうが、より楽しめるとわかりまして。
「じゃあ防音室を作りましょう」という話になりました。
■大森: 先ほども言いましたが、あの防音室の出来は本当に素晴らしいです。音圧の効果を高めるだけでなく、外に音が全く漏れないので、プレイヤーが安心して自分の世界に没入できるのですよね。『マックスボルテージ』というコンテンツに非常にマッチしていると思います。
●田宮: 音響の細かい調整も気が利いています。体験中にマイクがスピーカーに近づくとハウリングが起きてしまうのですが、体験者の位置を常に追いながら裏でハウリングを起きにくくするサウンド処理が入っていたりして、ここがライブ会場であるという臨場感を邪魔しない、自然な音響環境を再現していると思います。
■大森: いつも悔しく思うのですが、サウンドの凄さ素晴らしさって書面では絶対に伝わらない。実際に体験してもらうしかないのですよね。
■大森: 『脱出病棟Ω』※8は、施設の中にいると男女問わず常に悲鳴が上がっていたことを覚えています。いい意味で、入る前からお客様が本気で怖がっている様子が伝わってきました。
車椅子に乗っていることで、動けるけど自由自在ではないもどかしさ。時々、ちょっと離れた場所から悲鳴が上がるそのタイミング。などなど、全てのさじ加減が絶妙で、非常に良く考え抜かれたゲームデザインです。
この怖さを引き立てている筐体を作る上では、どんなところに注力しましたか?
●石井雅: より恐怖感を出すために狭い箱形の筐体にしましたので、安全面と防犯面を特に考慮しました。プレイヤーは目も耳も塞がれている状態ですから、それでも安心して楽しめることに気を配りました。

『脱出病棟Ω』
●田宮: 気が利いているなと思ったのは、シート周りに配置されている物が全てクッション素材で作られていることです。プレイヤーの大半が驚き叫び、中には本当に暴れだす人も居るくらいですが、それでもけが人が全く出ませんでした。最初からそこまで想定してあったのですね。
●石井雅: 加えて、どういったタイミングでどんなアクションを起こせばより怖がってもらえるか、検証を重ねました。例えば、座面の下に振動装置が入っていて驚かせるタイミングで震えるようになっているのですが、気がついていただけましたか?
■大森: いえ、全く気がつきませんでした! 本当に怖くて、それどころではなかったです。(笑)
筐体外観のデザインも非常に秀逸だと思っています。映像はVRゴーグルですし、ホラーという性質上、中の様子は見せられない。それなのに、筐体の外観を見るだけで充分に怖さが伝わってくる、すごいことです。
●酒井: 現場でお客様があの黒い筐体を見た時に、「この筐体でどんな体験ができるのか」をどう伝えるか、ID担当者はすごく苦労していました。病院を模した意匠や、「ホラー実体験室」のコピーなどは、試行錯誤の結果です。
●田宮: 明滅するランプの演出が、気持ちを煽っているように感じてすごく効果的ですよね。運営マニュアルには、「無理強いしている場面を見たら止めて欲しい」と書いてあるくらい、本当に怖いコンテンツに仕上がっています。
■大森: 個々のVRコンテンツの内容に対して、IDの立場から「ここはこうした方が良いのでは」と言うような提案はしましたか?
●酒井: どのコンテンツも魅力的かつ完成度も高い内容だと思いましたので、基本的には「どういった体験ができる装置なのか」を伝えることに注力してバナーなどをデザインしました。
■大森: 「ホラーはVRと相性がいい」という一言だけでは片付けられない、コンテンツとして非常に高い完成度だと誇って良いでしょう。
■大森: 『ガンダムVR ダイバ強襲』※9(以下、『ガンダム』)は8月末の設置とかなり遅かったわけですが、初期のプランには無かったということですか?
●田宮: はい。出展場所が決まった後、上層部から「なぜお台場なのにガンダムが無いのか?」と言われました。同時に、「夏休みに間に合うなら予算をつける」とも。個人的にもガンダムをやりたかったので、苦しいスケジュールでしたが引き受けました。(笑)
●福冨: 実質2ヶ月半と、記録的な短期間で作り上げたコンテンツです。一番苦労したのは、体験中にプレイヤーが台から滑り落ちてしまうことへの対策でした。腰のベルトは苦肉の策でしたね。
■大森: それだけの臨場感があるからこそ、ジッとしていられないのだと思います。自分が見た限りでは、プレイヤーがベルトに戸惑う様子は無かったですよ。
れに実際に乗ってみると、すごく上昇感を得られてビックリしました。「おおー!」って声を上げてしまうくらい。でも現実では数cmしか上昇していないのですよね。
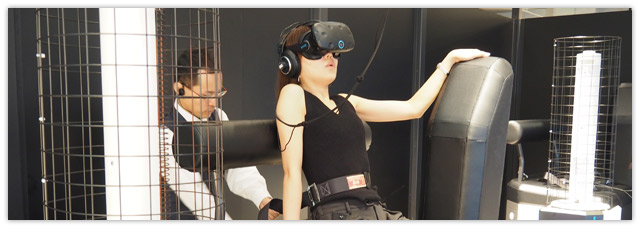
『ガンダムVR ダイバ強襲』
●福冨: 振動を生み出すモーター制御で工夫しています。特性の違う複数のモーターを使い、シチュエーションに合わせて作動制御しています。
それに、何と言ってもサウンドの力ですね。『ガンダム』には入力装置が一切無いので、ほぼサウンド効果だけであの臨場感を演出していると言っても過言ではありません。
■大森: 風が吹き付ける仕掛けがあるじゃないですか。最初はちょっと笑ってしまったのですが、これも意外と臨場感に繋がっています。風が吹く、熱を感じると云ったちょっとした仕掛けが効果的なのだな、と思います。
●福冨: 『高所恐怖SHOW』※10でも、エレベーターから屋上に出たところで風を当てていますが、本来であれば強風を当てたいところでも、VRの場合は弱い風であっても映像と組み合わせることで、まるで強風に当てられているかのような臨場感を与えることができます。『ガンダム』ではそれに加えて、ビームサーベルが相手の武器と交じり合う際、目の前にあるビームサーベルの熱感を出すためにハロゲンヒーターを使用しています。これも臨場感を出すために、映像に合わせてすぐに熱を出せる熱源が必要で、色々と検討した結果ハロゲンヒーターを採用することになりました。
■大森: 『高所恐怖SHOW』を体験して気がついたことなのですが、助け上げたネコがずっとこっちを見ているのですよね。小技が利いていると言いますか、凝っているなあと非常に感心しました。
●柿沢: 今、「小技」とおっしゃった部分が実は非常に重要でして、VRコンテンツでは「いかにして没入感を持続させるか」が大事です。小さな演出の積み重ねがプレイヤーにリアリティを感じてもらえるコツなのです。

●柿沢 高弘(かきざわ たかひろ)
ソフトエンジニア
『装甲騎兵ボトムズ バトリング野郎』ディレクター
■大森: 小技と思ったところは実は大技なのですね。
●福冨: 『高所恐怖SHOW』のプレイヤーが乗る板も左右にガタを付けており、実際には1cmも傾いていないのですが、その小さな動きがあるだけで得られる臨場感が段違いです。
■大森: 『スキーロデオ』の白い息や、『ガンダム』の温かい風も、臨場感を少しでも上げるための工夫ですね。
改めて、皆さんに色々と話してもらって、『VR ZONE』はバンダイナムコグループだからこそ実現できた施設なのだということに確信が持てました。
●田宮: 世界初のVR施設でしたから、予測できない事態の発生は必ずあります。しかしVR以外の部分も含め、事前に予測し得るトラブルなどが未然に防げているというのは非常にすごい事だと思います。
■大森: 旧ナムコの頃から綿々とアーケードゲーム筐体を作り続けてきたノウハウがありますからね。
他社でも突貫工事で作るだけなら作れるけれど、それでは「3日で壊れました」ということになりかねない。とてもお店に出せる物ではありません。むしろ何か作った経験のある人ほど、『VR ZONE』の筐体の作りは優れていることが理解できるはずです。
●田宮: それに、BNSのハードメンバーに開発をお願いすると、企画の制限を取っ払ってくれる感じがしました。あれだけ動く筐体をあの短期間で作れる会社は他に無いと思います。
VRはまだまだ、あらゆる可能性を模索しながらコンテンツを作っていく時期です。多少無理無茶な要望であってもBNSのメンバーなら実現してしまうので、結果今回も面白いコンテンツを揃えられましたし、これからも面白いものが出来てくる予感がします。
■大森:私も今後出てくる新しいコンテンツを楽しみにしております。本日はありがとうございました。
『VR ZONE Project i Can』
VR ZONE Project i Canとは
株式会社バンダイナムコエンターテインメントが展開するプロジェクト、「Project i Can」から生まれた、VRエンターテインメント研究施設です。VRをはじめとした最新の技術と体感マシン開発技術をかけあわせることで、「やりたい!けど実際はムリ」という「夢・好奇心」を、ホンモノの体験として実現し、多くの人びとに驚き、楽しんでいただける新しいエンターテインメントの提供を目指すというプロジェクトのメッセージを体現すべく、2016年4月15日~10月中旬までの期間限定で営業を行っています。今後も体験いただいたお客様からのご意見を活かしながら、さらなるVRの可能性を追求していきます。
http://www.namco.co.jp/company/NEWS/others_facility/20160707_1000_C1211.html
○『VR ZONE Project i Can』公式Webサイト
https://project-ican.com/
○『VR ZONE Project i Can』公式Twitterアカウント
https://twitter.com/project_ican
※7 ©創通・サンライズ
株式会社バンダイナムコエンターテインメントの製品です。
※8 ©Bandai Namco Entertainment Inc.
※9 ©創通・サンライズ
株式会社バンダイナムコエンターテインメントの製品です。
※10 ©Bandai Namco Entertainment Inc.
開発協力:株式会社クレッセント